2025年6月4日、京都・総合地球環境学研究所にて、『総合地球環境学研究所SceNeプロジェクト・日本海洋文化総合研究所共同企画―座談会』が開催された。本座談会では、「海と人の関係性」をあらためて見つめ直すために、両研究所からの発表とそれに基づく議論が交わされた。総合地球環境学研究所(以下、地球研)から渡邊剛、山崎敦子、後藤明、日本海洋文化総合研究所(以下、海総研)からは池ノ上真一、石村智、栗原憲一、美馬のゆり、大内さおり、石丸優希、そして海ノ民話のまちプロジェクト及び海と灯台プロジェクトを企画運営する株式会社ワールドエッグス代表取締役・波房克典、「海と灯台プロジェクト」事務局から阪口大輔が参加した。

地球研からは、サンゴ礁の地質学研究を起点に、科学・アート・場(地域)を重ね合わせながら共創の可能性を探る取り組みが紹介された。一方、海総研からは、各地に伝わる海の民話をアニメーション化するプロジェクトや、灯台を題材にした空間や記憶の再解釈に関する実践が共有された。
それぞれの立場やアプローチは異なるものの、「人間は自然といかに向き合ってきたか」「記憶をどう語り継ぎ、未来へと手渡していくか」といった根源的な問いが通底する。発表と対話を通し、海と人との関係をとらえ直す多様な視座が浮かび上がった。
5万年前の海から「語り」が始まる

地球研・渡邊剛氏の発表は、地質学者としての自身の原点から始まった。研究対象は鹿児島県喜界島のサンゴ礁。かつては一時的に地域に入り、情報を持ち帰って外部で分析する「パラシュート型研究」を行っていたが、島に通い続ける中で「地域とともに考える科学」の必要性に気づき、研究のあり方を根本から見直すことになったという。サンゴ礁は、樹木の年輪のように、とてつもなく長い環境の記憶を骨格に刻む。それは、地質学的なスケールと、人間の生活時間をつなぐメディアになりうると、渡邊氏は語る。サンゴは産卵し潮に乗って移動し、その過程で、骨の成長輪に環境の記憶を刻んでいく。数千年という長いタイムスパンで、サンゴ礁には過去から現在までの記憶が眠っているのだという。

一方で、私たちの社会はどうか。高齢化が進み、人口が減少する中でも、いまだに経済成長を追い求める現代の日本。人々の視線は、いつしか未来にばかり向けられるようになった。私たちは今一度、経済的な文脈から離れ、眼の前に存在する「場」や「時間」に、立ち返るべきなのかもしれない。そのために、渡邊氏が取り入れた新しい手法が「演劇」であった。
現在、渡邊氏は劇作家・平田オリザ氏を招き、地域住民や研究者、アーティストを巻き込んだ演劇プロジェクトを推進。演劇はどんなに長い時間も、遠く離れた空間も、サンゴのように自由に飛び越える。「5万年前の鬼ヶ島」を語ることも、「人間がサンゴになる」といった荒唐無稽な設定も、演劇の上では可能なのだ。こうして演劇プロジェクトは、フィールドワークの知見と結びつき、研究と表現、記憶と身体が交差する場となった。

また教育的観点からは、地域の人々・学生・研究者が共に演劇制作に関わることで、学ぶ側・教える側の境界が曖昧になり、対等な学びが成立したと感じる場面も多くあったという。このような実践に対し、美馬氏は、AI時代の教育という側面から言及した。「論文やレポートの作成やその採点といった既存の教育方法は、生成AIによって機能しなくなるかもしれない」。そう語る美馬氏は、今後ますます重要になる「問いを立てる力」や「他者と共に未来をつくる力」に対して、演劇をはじめとするロールプレイ型の学びが大きな価値をもたらす可能性を指摘した。

演劇とは、他者の視点を身体で体験しながら、「問い」を共有し、共に考える営みだ。科学とアート、そして地域という「場」を重ね合わせることで生まれる語りの共創は、民話にも通じる視点を私たちに示してくれる。それは、人が昔から続けてきた、本来の「学び」のかたちを取り戻す試みなのかもしれない。
見えない記憶を語る民話
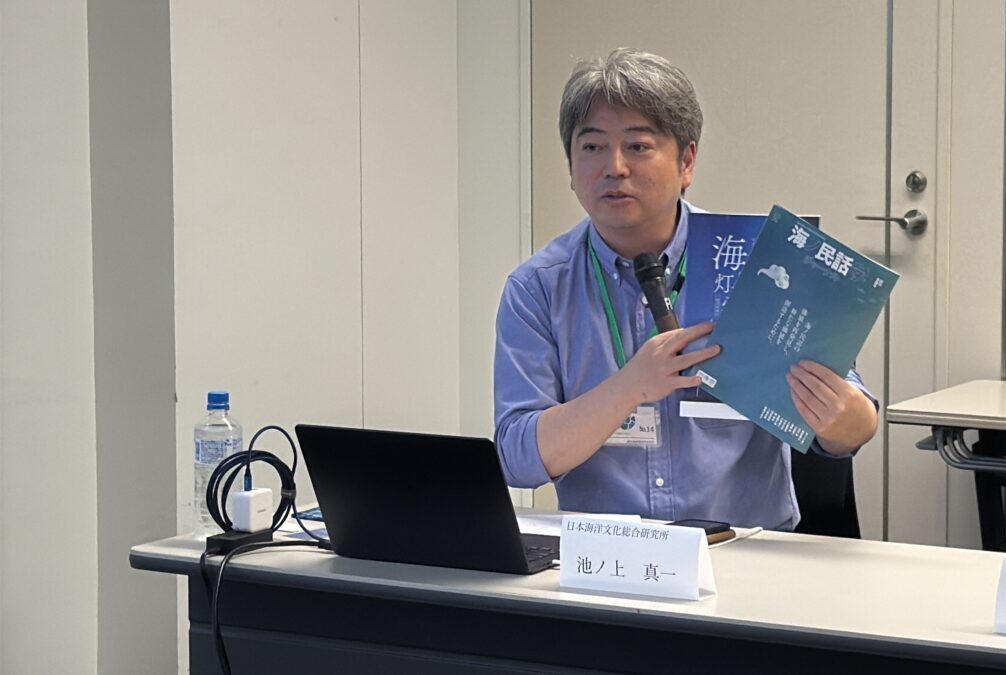
続いて海総研からは、池ノ上真一氏が『海ノ民話学ジャーナル 創刊準備号』にまとめられた内容を紹介。また、日本各地の海にまつわる民話をアニメーション化し、教育・観光・地域資源として活用するプロジェクトの動向についても発表した。その中で印象的だったのは、「民話とは何か」という問いかけに対して、登壇者それぞれの多角的な思索が交錯した点だ。

石村氏は、『浦島太郎』に描かれる竜宮城が、もともとは海の向こうにある「水平的な他界」だったが、時代とともに海の中深くにある「垂直的な異界」へと変化したことに触れた。民話には、時代とともに変わる世界観が内包されている。もともと民話は神話的な構造や、この世とあの世をつなぐ想像力を宿していた。見えない存在への畏れや敬意は、たとえば現代の『トイレの花子さん』や 『着信アリ』といった怪談にも共通しており、民話はそうした“異界”と人間との関係を描く装置でもあった。
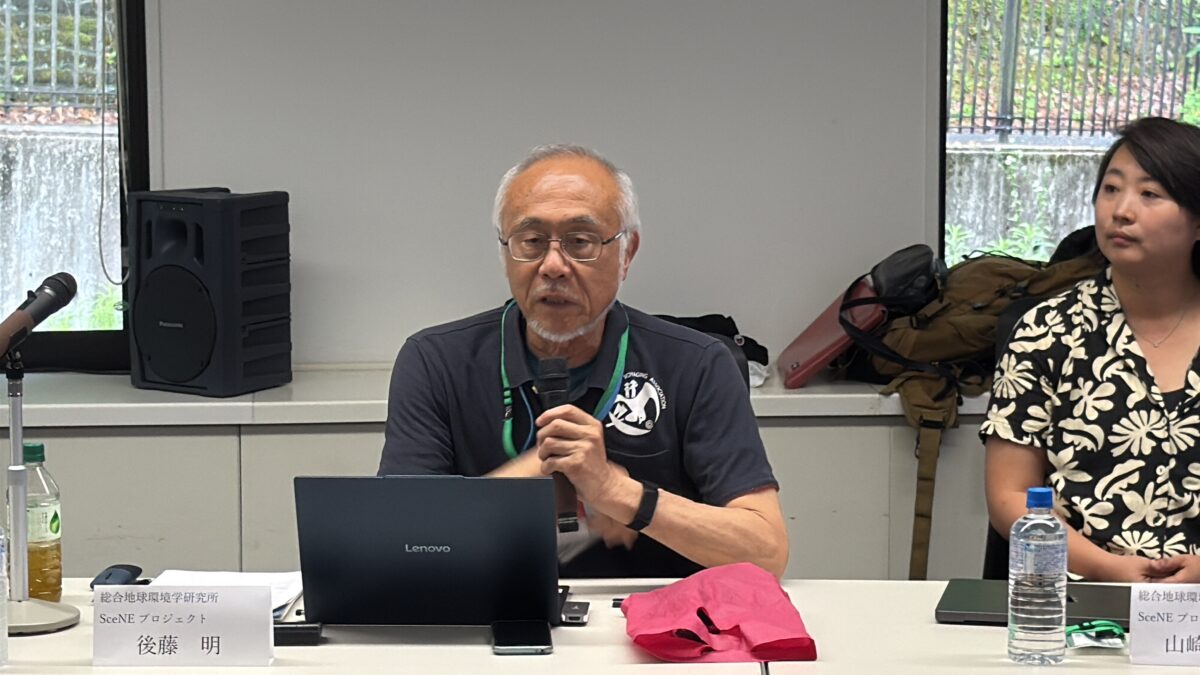
民話に内包されたこうした時代ごとの世界観の変化に対し、文化人類学と地球環境にも通じる後藤氏はより大きなスケールからの視点を提示した。後藤氏は、人類遺伝学や人類学の視点から、民話には「外から語りが持ち込まれて浸透していくようなグローバルな広がり」と「その土地の地質・気候・歴史と結びついたローカルな語り」が共存していると指摘。『シンデレラ』や『浦島太郎』に似た物語が世界各地に存在するのは、そうした影響の流通に加え、人類共通の思考様式を反映している可能性もあるという。

さらに、民話を現代の価値観から読み直す必要性についても、議論は広がった。ジェンダー観やDE&I、社会規範などの視点から、従来の物語に対する批判的な再解釈は避けて通れない。実際、アニメーション化に際しては、こうした観点を反映した新たな物語の構築が試みられている。その延長として、座談会の後半では「記憶と語りの継承」が主なテーマとなった。誰がどのように民話を語り継ぐのか。その過程で、無意識的なバイアスや“見えない力学”が作用していないか。たとえば、伝統的なジェンダーロールをそのまま映像化することへのリスクや、どの民話をアニメーション化するかを決める際に、特定の価値観や都合による選別が行われていないかが問われた。

こうした懸念に対し、海ノ民話のまちプロジェクトを企画運営する波房氏は、「扱う民話には、為政者がほとんど登場せず、民の生活や教訓、地理的背景が語られている」と述べた。制作にあたっては、自治体からの提案をもとに学びや継承性のある話を選定。地元の実行委員会が脚本段階から関わり、完成後は教育や観光など、地域での活用を前提としている。波房氏自身、民俗学研究において「記録の保存にとどまらず、どう活用するか」に課題意識を持ってきた。だからこそ、アニメーションとして有形化する際には、民話が本来もつ可変性や現代的意味の読み直しをどう担保するかが重要だと語った。
そもそも民話は、語り継がれる中で変化を重ねてきた存在である。物語は鑑賞され、解釈され、語り直され、共有されるというサイクルの中で再構築されていく。そのプロセスこそが、物語の“生命力”であり、現代にも民話という「語り」を生かし続ける力となる。アニメーションという手法もまた、次の世代に向けて民話を読み替え、新たなナラティブとして紡いでいく手段のひとつといえるだろう。
境界に立ち上がる灯台

さて、もうひとつのテーマが「灯台」である。参加者には『海の民話ジャーナル』と並んで、『海と灯台学』に関する冊子も手渡された。GPSが普及し、当初の存在意義を失いつつある灯台の価値をどう見つめ直し、残していくべきか。民話と同様に、灯台もまた「海と人をつなぐ装置」としてとらえることができるだろう。今回の座談会では、建築・地質・神話といった多様なレイヤーから、参加者の視点を通じて議論が深められた。
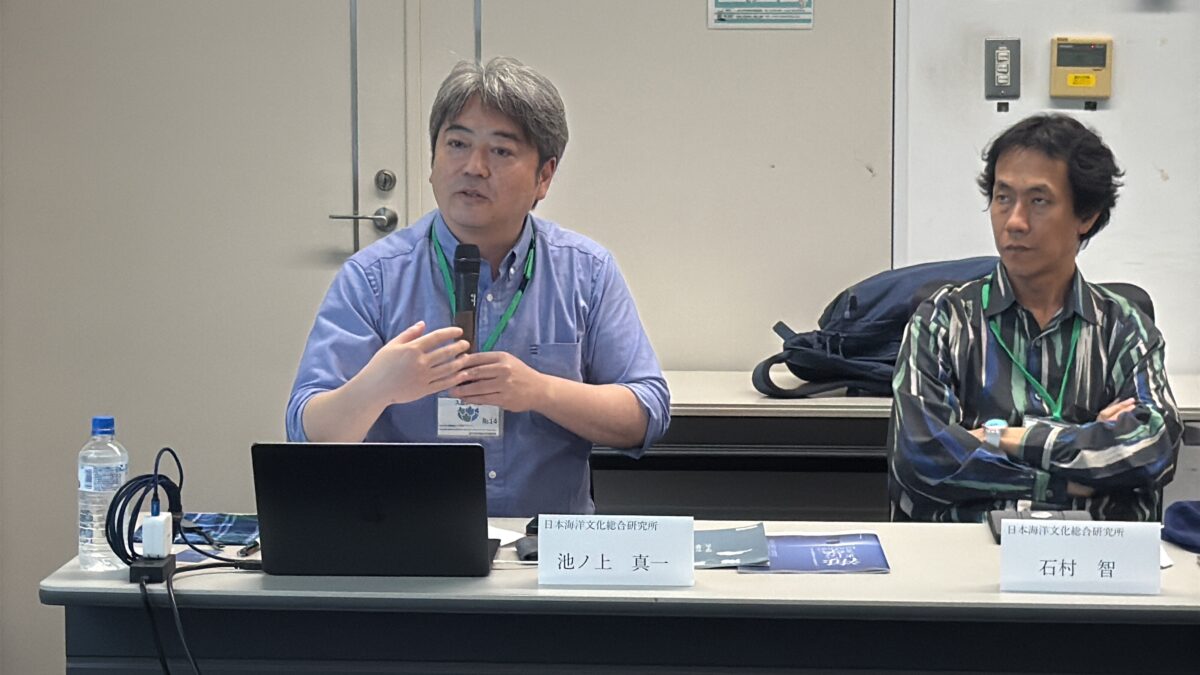
まず建築的な観点から、日本全国に立地する灯台の素材や構造の多様性が示された。白や赤に塗られた灯台の背後には、地域特性に応じた材質の違いがある。たとえば、石積み、木造、鋼製、コンクリート造などさまざまなタイプが存在し、とくに雪の多い北海道などでは特有の形状をもつ灯台もあるという。さらに灯台が立地する場所の地層や素材に注目すると、たとえば犬吠埼灯台の下に広がる地層は、一億年前の白亜紀のものであり、近隣の採石場で採れた地質素材が灯台の建設に使われているのだという。現存する灯台関連施設は全国で約3,200基に上り、これらをデータベース化して分類・分析しようとする試みも進んでいる。

また、灯台の歴史的意義については、明治初期に欧米列強の要請を受けて建設が始まった経緯が言及された。江戸期の日本では、夜間航行や沖乗りが一般的ではなかったため、光による航路誘導装置としての灯台の必要性は乏しかった。だが、条約締結を契機に、特に米中貿易との接続を意識した灯台建設が求められるようになった。
その一方で、「日本に灯台のようなランドマークは、それ以前には全くなかったのか?」という問いから、古代の航海文化の再検討が行われている。石村氏は、日本の航海はもともと沿岸を地形的ランドマークに沿って進むスタイルで、カヤックのような小舟からは水平線の可視範囲が限られているため、地上の視認可能な目印が極めて重要であったことを指摘する。この文脈で注目されたのが、全国に点在する前方後円墳などの古墳群である。丹後半島や牛窓に残る古墳群など、とりわけ内海や日本海側の沿岸部に分布する古墳のいくつかは、海からの視認性の高い場所に立地し、古代の港湾との関係性が浮かび上がる。時代は異なるものの、明治期の灯台と同様、古墳も海からよく見える立地に築かれているのだ。背景にはいずれも対外交易の活性化があり、宗教的、政治的な要素とともに、古墳が航路指標的な役割も担っていた可能性がある。
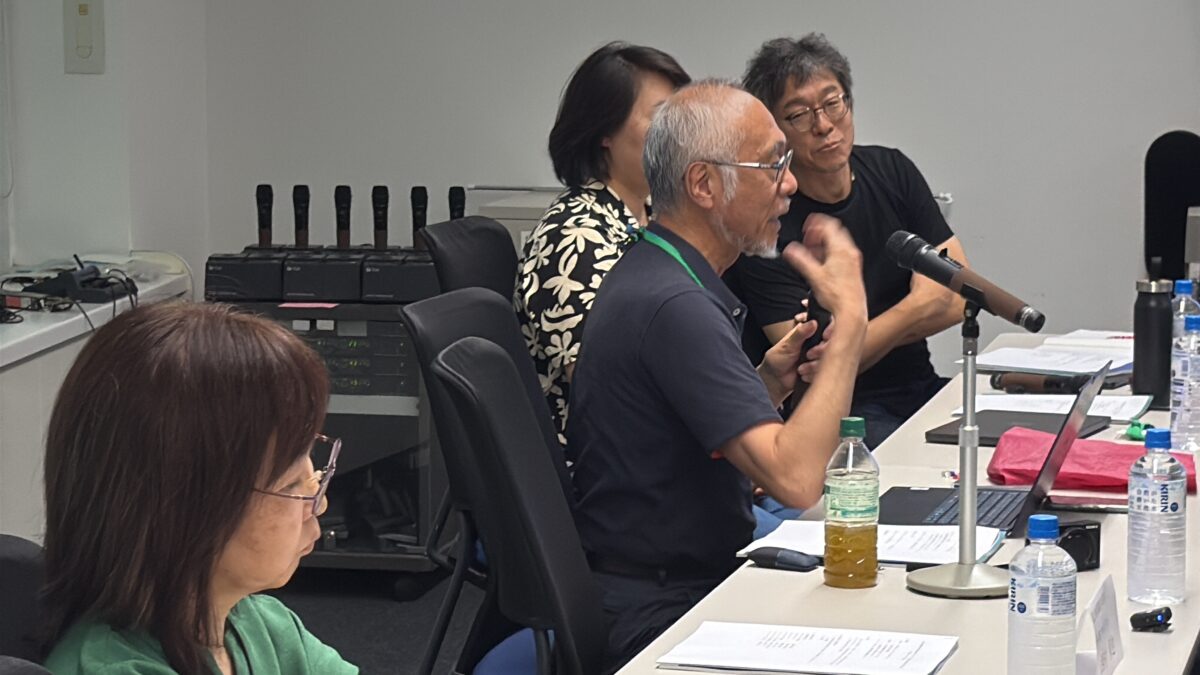
このように、灯台も古墳も「視認されるランドマーク」である点では共通しているが、それが「誰にとっての目印であったのか」という視点は重要だ。栗原氏は、視認性とは単に物理的な可視性だけではなく、それを見る主体によって意味が変わると指摘する。見上げる者、訪れる者、あるいは航行中に視界に捉える者。その立場によって灯台や古墳の意味は異なってくる。そうした複数の視点の交差点にこそ、文化的な解釈や活用の可能性が広がるのではないかという問いかけである。
「灯台は海から見えるランドマークであると同時に、陸上から訪れる歴史的な場所でもある。そこには地質的・文化的時間の両方が折り重なっている」と語る石村氏の言葉には、民話が内包する「見えない記憶」にも通じる響きがある。歴史に記録されない人々の営みや思いを伝える民話と同様に、見えないものを映し出すのが、象徴としての灯台の役割なのかもしれない。まさに灯台とは、海と陸、過去と現在、見えない世界と私たちをつなぐ「境界」に立ち上がる装置であり、それゆえにこそ今、新たな語りを引き出す存在として見直されていくべきなのだ。
海と人の向かう先
今回の座談会を通じ、参加者たちは「海と人との関係」をめぐって、多様な視点から議論し、互いの思考を深め合った。民話のアニメーション化や、灯台の保存と再活用、そして地域の記憶や自然との関係を描く演劇の実践。それらはすべて、土地に根ざした営みに新たな命を吹き込むものとして共有された。対話を重ねる中で、こうした取り組みに込められた思いや背景が明らかになり、海と人との関係を見つめる共通のまなざしが浮かび上がっていった。
海の民話は「語り継がれるために変化し続ける」ものでもある。現在進行形でアニメーション化され、教育現場や地域資源として活用される民話は、新たなかたちの“海の記憶”に変わり始めている。一方で灯台もまた、役割や技術的な意義を変化させながら、新たな意味づけを与えられつつある存在だ。保存や再活用の動きのなかで、地域の記憶や文化と結びつきながら、まさに今語り直されようとしている。
民話と灯台。そのどちらもが、人と海との関係を照らす光であり、記憶を刻むアーカイブでもある。時とともに少しずつ変わっていく民話と、変わらずにそこに立ち続ける灯台。その間に揺れる“海と人”の物語を、私たちはいかに受け取り、語り継いでいけるだろうか。
ライター 佐藤真生
サイエンスからエンタメまで横断するライター。体感型科学マガジン『Tangible Scientific Design』編集長。眞魚名義でラッパーとしても活動し、作詞・作曲を手がける。

